今回はBLITZ2の中でも特に謎が多い「安定化係数(Stabilization Factor)」についてです。
安定化係数がApexでエイムアシストとどのように相互作用するのか、そしてエイム全体にどんな影響を与えるのか。さらに、海外・中国の専門コミュニティや実機検証を踏まえた実使用の結論までまとめています。
「BLITZ2の“安定化係数”がよく分からない」
「アシスト弱く感じるのって設定のせい?」
こんな疑問を抱えている人向けに、海外フォーラム・中国コミュニティ・海外専門家の検証内容を元に、最も正確で専門性が高い完全版マニュアル”を作りました。
BLITZ2を使っているプレイヤーなら、絶対に知らないと損する内容なので必見です。
この記事は、Apexで少しでも設定を最適化したい勢に向けて、仕組み・理論・最適値・応用方法までワンストップで理解できる構成です。
BLITZ2利用者が必ずつまずく“安定化係数の本質”を、この記事で完全理解できます。
関連ガイド:BLITZ2のデバッグ設定も合わせて最適化する
BLITZ2を最大限に活かすために、デバッグ設定の理解は欠かせません。
安定化係数と組み合わせることで、視点制御の精度が一気に向上します。
→ BLITZ2 デバッグ設定はこちら
PR:この記事には広告を含みます
安定化係数(Stabilization Factor)とは何か?【BLITZ2独自の入力補正】

BLITZ2の安定化係数は、スティック入力に“フィルタリング(平滑化)”をかける機能で、視点のブレやノイズを抑える役割を持ちます。
👉️設定値の範囲
- -10 ~ +10
- 0がデフォルト(補正なし)
👉️値の方向で挙動が根本から変わる
- +方向:安定化を強める(揺れが減る)
- −方向:レスポンスを強める(反応速度が上がる)
BLITZ2完全ガイドはこちら▼
仕組み:安定化係数は“スティック信号にかかるデジタルフィルタ”
安定化係数の正体を平易に言うと、スティック入力に対してかかるデジタルフィルタ(平滑化処理)です。
BLITZ2はスティックからの入力信号をそのままゲームへ送るのではなく、内部で一度“処理”してから出力しています。この処理の強さを数値で調整できるのが安定化係数です。
+方向(フィルタ強)
数値をプラス方向へ上げるほどフィルタが強まり、
- スティックの細かな揺れを吸収
- 微小な震えによる“視点ガタつき”を防止
- 精密エイム時やリコイル制御時に照準がブレにくくなる
という効果が生まれます。
特に中〜遠距離でのリコイル制御時に“照準の安定感”として実感しやすい動作です。
−方向(フィルタ弱)
数値をマイナスに振るほどフィルタが弱まり、
- スティックの動きが“生”に近い状態で出力される
- 微細な揺れや入力のばらつきもそのまま視点に反映
- 反応は鋭いが、安定性は下がる
という特徴が現れます。
● 結論:安定化係数とは「入力信号の安定化レベル」を調整する設定
- +方向 → 入力を滑らかにし、視点を安定化
- −方向 → 入力をダイレクト化し、揺れも含めて出力
メーカー視点では、プレイヤーの好みやプレイスタイルに合わせて“入力信号のフィルタ強度を調整できる機能”として実装されていると考えられます。誰でも自分だけのエイム感覚を追求できるようにするための仕組みです。
おすすめ記事:Apex ボタン配置の最適解
安定化係数で視点が安定したら、次は操作性の改善です。
ボタン配置の最適化は火力・生存率の両方に直結します。
→ Apex ボタン配置ガイドはこちら
安定化係数がエイムに与える影響とApexエイムアシストとの相互作用
Apex Legendsでは、スティックが動いている間のみエイムアシストが強く働くという仕様があります。このため、安定化係数の設定は“アシストの感じ方”に大きな差を生みます。
エイムアシストの仕組み(超重要ポイント)
Apexのエイムアシストは以下の2つの要素で構成されています:
- エイム減速(スローダウン):敵付近で視点が減速する補正
- 旋回補助(追従アシスト):スティックが動いていると敵の動きに合わせて視点が追尾する
特に大事なのは:
スティックが微小でも動いている時だけ、追従アシストが強く働く
つまり、
- 微入力が残る設定 → アシストが粘り強く効く
- 入力が静止しやすい設定 → アシスト追尾が働かない
この性質が安定化係数と密接に連動します。
安定化係数マイナス方向は“アシストが最も噛む”
安定化係数を下げるとフィルタが弱まり、スティックの揺れがそのまま視点に反映されます。
その結果:
- 視点が“完全には止まらない”
- Apex側で「入力が継続している」と判定
- 追従アシスト(旋回補助)がほぼ常時働く
体感としては、
- 敵に吸い付くような“マグネット感”
- レレレ相手も追いやすい
- 近〜中距離戦でアシストの粘着が最強レベル
Redditや中国コミュニティでも、
「Apexでは安定化係数を下げるとアシストが爆発的に感じられる」 という検証が複数共有されています。
StickAnalyzerの解析でも、
マイナス設定 → 微細揺れ成分が増える →アシストが働き続ける というデータが確認されています。
MOJHON最新Pad、RAINBOW3も安定化係数がアプデで加わり価値爆増中です👇️
安定化係数プラス方向は“アシストを弱く感じる”
フィルタが強くスティックの微振動が消えるため、視点がピタッと止まりやすくなります。
Apex側では:
- 「入力が止まっている」→追従アシストが働かない
結果:
- 敵が動くと置いていかれやすい
- アシストの“粘り”が感じられない
- 遠距離の精密射撃には良いが、近距離追いエイムが弱体化
実際に、
「安定化係数を上げたらアシストが弱く感じた」 という声は海外でも多く、これはゲーム仕様が理由です。
超重要:アシストの“強さ”は変わらない
安定化係数を上下しても、Apexのエイムアシストの数値自体は変化しません。
変わるのは:
- あなたの入力の状態(動いているか・止まっているか)
- その結果、アシストが発動しやすいかどうか
安定化係数弱め → 微入力が残る → 追従アシストが働き続ける
安定化係数強め → 静止しやすい → 追従アシストが働かない
ただそれだけの話ですが、体感差は非常に大きいです。
✅️過去のBLITZ2エイムアシスト記事はこちら▼
海外・中国コミュニティの検証まとめ
【Reddit】
- StickAnalyzerを使用した解析で、マイナス設定は“微揺れ増加→アシスト強く感じる”と報告
- プラス設定は“静止が増える→追従アシストが弱まる”という結論
【海外上級者(Jacster氏)】
- -9設定はApexで線形性と追従性能が“最高クラス”と評価
- センター補正と併用でさらに安定したと報告
【中国コミュニティ】
- 防抖系数は“微入力をどれだけ残すかの調整”という共通認識
- Apex向けには負方向を推す声が多数
アシストを強く感じる / 弱く感じる条件まとめ
| 状態 | 設定 | 体感 | 理由 |
|---|---|---|---|
| アシスト最強 | 安定化係数 -5〜-1 | 粘り・追尾が強い | 微入力が多く追従アシストが常時発動 |
| バランス型 | 安定化係数 0〜+2 | 自然で扱いやすい | 微入力も静止も両方ある |
| アシスト弱め | 安定化係数 +3〜+6 | 追いエイムが弱い | 静止しやすく追従アシストが働かない |
結論:Apexでアシストを最大化したいなら“マイナス方向”
- アシスト頼りの戦闘が好きなら → 迷わずマイナス設定
- 遠距離の安定性を重視するなら → プラス設定
安定化係数は、Apexのエイムアシストの“入り方”に最も影響を与えるBLITZ2の設定です。自分のスタイルに合わせて最適ゾーンを見つけることが勝率アップにつながります。
あなたのプレイスタイル別「最適ゾーン」
| プレイタイプ | 推奨値 | 効果 |
| 初心者・安定感重視 | +3〜+6 | 視点が安定、リコイル楽 |
| 中級者(バランス型) | 0〜+2 | 軽すぎず重すぎない万能 |
| 上級者(近距離強め) | -3〜0 | 追いエイムが鋭い |
| ガチ勢・超反応タイプ | -10〜-5 | アシスト最大活用、反応最速 |
組み合わせると“最強”になる設定(相乗効果の塊)
安定化係数をマイナス方向に振った時、単体では揺れが増えやすい・暴れやすいという弱点が出ます。
しかし、海外勢が実際に行っている“鉄板セット”を併用することで、その弱点を完全に補い、アシスト最大化 × 操作安定 × 反応速度UP の三拍子が揃います。
ここではその3つを専門的に、かつ分かりやすく徹底解説します。
① デッドゾーンを小さくする(Deadzone)
目的:スティック中心の遊びを最小にして、反応を鋭くする
安定化係数をマイナス方向にすると、スティックの“生の揺れ”が出やすくなります。
その際にデッドゾーンを適切に小さく設定すると:
- スティック反応が速くなる
- 視点操作が軽くなる
- 微調整がしやすくなる
- 無駄な“空白操作”が減る
という恩恵があります。
特にApexは“入力が動いている時にアシストが働く”ため、デッドゾーンを小さくすることで:
「アシストが発動しやすい入力状態」を常に作れる
これが海外勢がデッドゾーンを0〜2%で運用する理由です。
② スティック曲線を低入力域で緩める(レスポンスカーブ調整)
目的:マイナス方向の暴れを抑え、滑らかな初動を作る
安定化係数を下げると、入力の鋭さが増す反面、初動が“ピーキー”になりがちです。
これを補うのがスティック曲線(スティックレスポンス)のカスタム設定です。
特に有効なのは:
- 低入力域(序盤)を“緩やか”にする
- 中入力域〜高入力域は直線的(リニア寄り)にする
こうすることで:
- 視点の初動が暴れない
- 敵を捉える時の“最初の動き”が安定
- 追いエイム中の細かい調整がしやすい
- それでいて高速ターンの反応は落とさない
結果として、
「アシストが強く働く状態 × 視点の初動安定」 を両立できます。
海外勢が“リニア寄りのカーブ”を好むのはこのため。
③ センターゲインとの併用(Center Gain)
目的:中心付近の入力精度を最大化し、微調整をコントロールしやすい状態を作る
センターゲインは BLITZ2 独自の高度な設定項目です。
ただし この項目はユーザーによって「感じ方」「捉え方」が大きく分かれる ため、まずはその点を前置きしておく必要があります。
一部ユーザーは“感度の変化・アシストの強まり”を体感している
センターゲインを調整した際に、
- 微入力がより滑らかになった
- トラッキングの喰いつきが増した
- エイムアシストが強くなったように感じた
という報告があります。
これは 中心〜低入力域(0〜20〜30%)付近の入力の入り方が変わる ため、
“アシスト帯に入りやすくなる”という体感的な現象が起きるためだと考えられます。
この体験があるユーザーは、
「センターゲイン=微入力のブースト/初動感度の最適化」と理解する傾向があります。
一方で、より多数派のユーザーは「ドリフト補正(中心点の安定化)」として活用している
多くのレビュー・技術系コミュニティでは、
- センターゲイン調整で“中心点のズレ”が消えた
- 微ドリフトが改善した
- ニュートラル位置が安定した
という声が圧倒的に多く、
“センターゲイン=中心付近のオフセット(位置)補正”
として扱われています。
これは「中心点の揺れ」や「触ってないのに動く軽微なズレ」を抑えたい人にとって非常に効果が高く、デッドゾーンを最小運用したいプレイヤーからも評価が高い理由です。
筆者としての結論:実質“中心安定化(ドリフト補正)+微入力の最適化”の両面がある
構造的な内部仕様がメーカーから完全公開されていない以上、断定は避けるべきですが、
- 実際の体験談
- 技術者の解析投稿
- 海外レビュアーの報告
- 中心点補正として効果がある例の多さ
これらを総合的に見ると、
センターゲインは「中心付近の安定化(実質ドリフト補正)」としての役割が最も強い
と考えるのが妥当です。
同時に、
中心域の入力の入り方も変化するため、
“アシストが強く感じる”というユーザーが一定数いるのも事実です。
つまりセンターゲインは、
「位置補正 × 微入力最適化」
この2つの性質を併せ持つ設定項目、とも言えることができます。
センターゲインをこのセットに併用すると何が起きるのか?
安定化係数をマイナス方向に振ると、
- スティックの生揺れが表に出やすい
- 初動がピーキーになりやすい
という弱点があります。
ここにセンターゲインを加えることで:
- 中心の微揺れを均してくれる
- 初動の暴れが消える
- デッドゾーン極小設定(0〜2%)でも安定
- トラッキング中の細かい“刻み”がやりやすくなる
- 遠距離の一定リコイルが安定
つまり、
マイナス設定の暴れを“中心域の制御力”で中和し、
アシスト最大化 × 初動安定 × 微調整安定 を同時に成立させる役割を持つ
このため海外では
「安定化係数 -5〜-10 × 低デッドゾーン × センターゲイン微調整」
がセットとして使用されているケースがあるのかもしれません。
Apex向け “最終おすすめ設定” 完全まとめ(2025最新版)
海外勢で実戦で最も強い構成の中でも紹介されていたものに加え、筆者自身も試してみて
効果を感じた最終的なオススメ設定をまとめました。
”強アシスト×初動安定×トラッキング最強”の構築例です。
| 項目 | 推奨値 | 理由・効果(Apex向け) |
|---|---|---|
| 安定化係数(Smoothing) | -5 〜 -10 | ・スティック微入力が残りアシストが噛みやすい・追従力(粘り)が最大化・近〜中距離の吸い付き感が最強 |
| デッドゾーン | 0 〜 2% | ・入力反応が鋭くなる・「動いている判定」が出やすくアシストが発動しやすい・海外勢は デッドゾーン 0% が標準 |
| センターゲイン | (0,3) 〜 (0,7)おすすめ:(0,7) | ・微入力のザラつきを整えて初動が安定・中距離トラッキングが滑らかになる・安定化係数- の弱点(ピーキー)を中和 |
| スティック曲線(Curve) | Point1: (30,20)Point2: (80,82) | ・初動(0〜30%)が緩くなり暴れを防ぐ・中盤はリニアでアシスト追従が最大化・終盤は鋭いので高速ターンにも対応 |
| 最適化の目的 | 強アシスト × 初動安定 × トラッキング最強 | ・安定化係数- のメリットだけを抽出・デメリット(暴れ・硬さ)を完全相殺 |
この基準をベースにあなたの感覚を落とし込み、自身の最適化設定を見つけられるキッカケに
なれば幸いです。
■ まとめ:安定化係数は「アシスト」か「精密度」の二択
- +方向 → 精密度UP(安定型)
- −方向 → アシスト噛みやすい(攻撃型)
Apexは“視点が動いている時にアシストが乗る”ゲームなので、マイナス方向ほどアシストの恩恵は得やすい。
一方、+方向は“視点を綺麗に保ちたい人”に向いています。
最終的にはあなたのプレイスタイル次第。BLITZ2は設定次第で性能が化けるので、ぜひこの記事を活かして自分だけの最適解を見つけてください!
▼ あとがき
BLITZ2の安定化係数は、超ニッチで奥深い機能です。 この記事が、あなたのApexの勝率アップにつながれば嬉しいです。
もっと詳細なカスタム例や、他項目(デッドゾーン/曲線/安定化係数の相互作用)の記事も続けて作っていく予定なので、気になる人はチェックをお願いします!
最後に:撃ち合いの勝率を「物理的」に底上げしよう
「設定」はソフト面の強化ですが、本当の無双状態に入るには「ハード面の強化」が欠かせません。
特に今、個人的に「エイムアシストがバグレベルで吸い付く」と話題なのが、静電容量式センサーを搭載した最新PADのRAINBOW3です。
私も実際に使ってみて、「エイムアシストの範囲が広がった?」と錯覚するほどの操作感に驚きました。
「今のPADがボロボロ」「もっと楽に敵を溶かしたい」という方は、ぜひ私の検証結果をチェックしてみてください。道具一つで、あなたのAPEXライフが劇的に変わりますよ!
スティックテンション調整が神の拡張ボタン豊富なPadはこちら👇️
最新環境まとめ:シーズン27武器アップデート
今シーズンの武器環境を理解しておくと、設定の方向性も決めやすくなります。
G7やR-99などアシストの恩恵が大きい武器との相性も解説しています。
→ シーズン27メタ武器はこちら



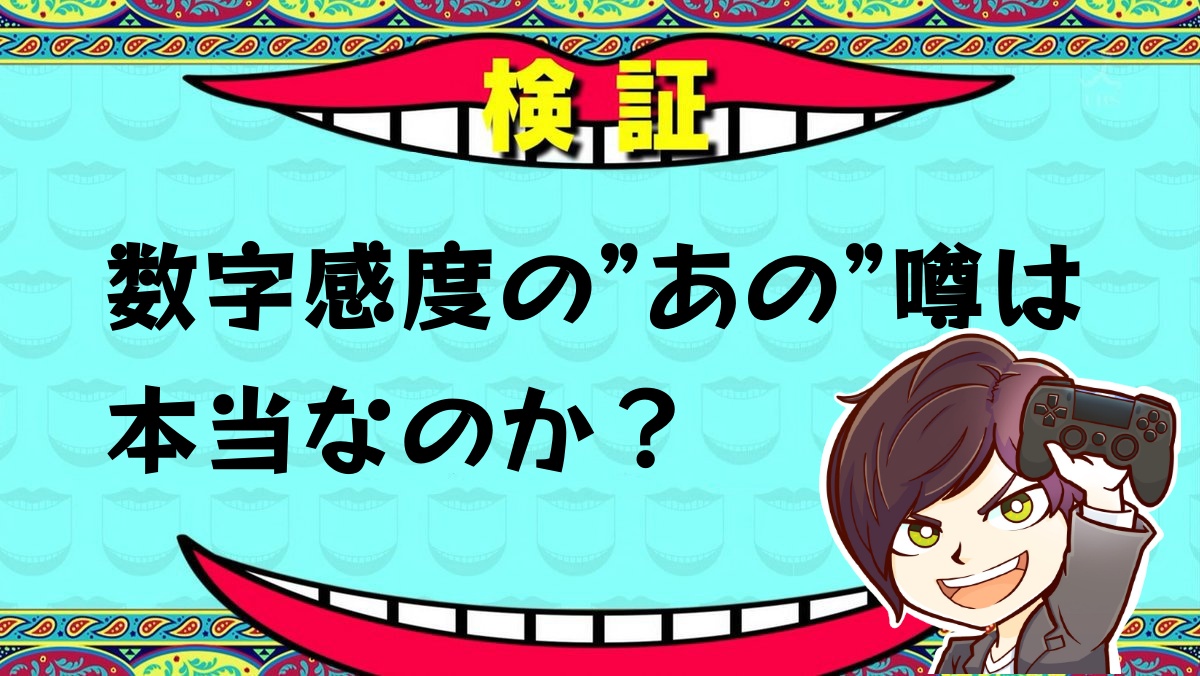




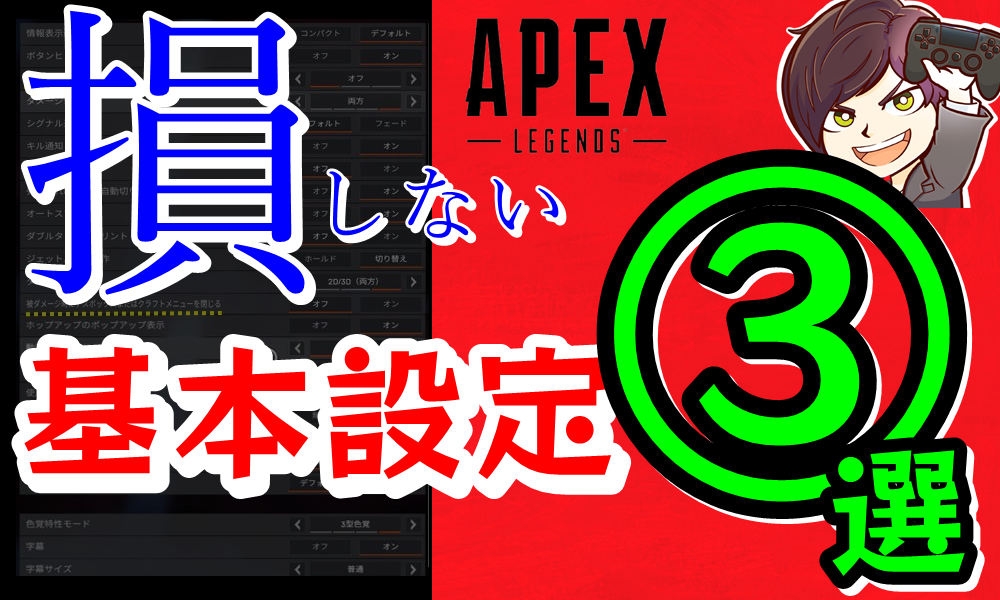



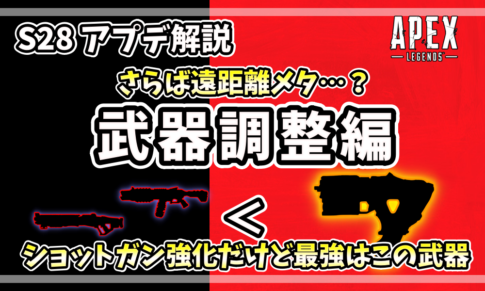
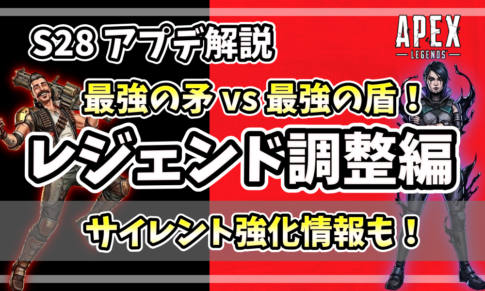


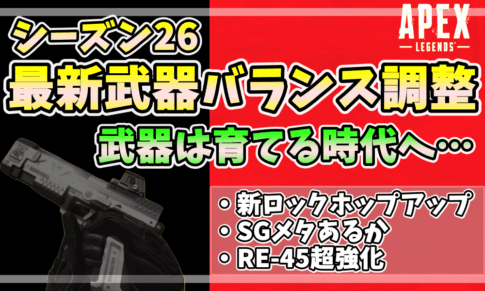




どうも!